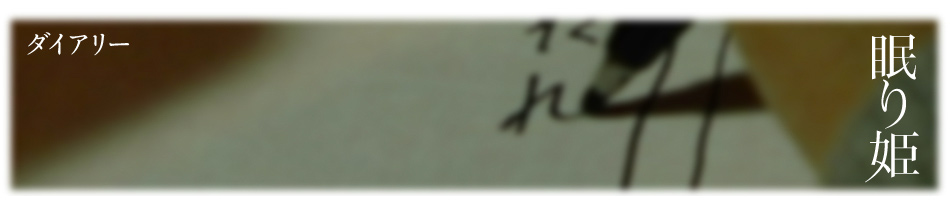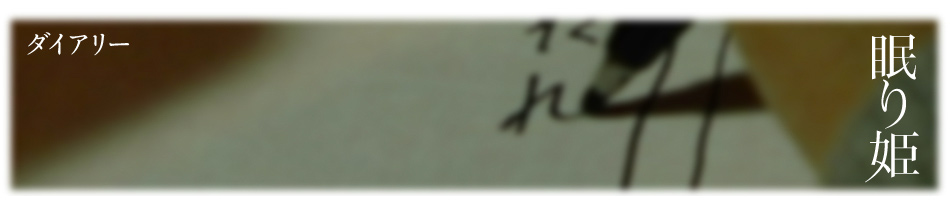|
訃報を知らせてくれた北岡さんが私の声を聞くなり、わあっと電話の向こうで声を上げ、
「ごめんなさい。七里さんの連絡先が分からなくなってて。倒れたときすぐに知らせられず。間に合わなかった」と言ったのだが。
不思議と悲しい気持ちにならなかった。
信じられないという思いとともに、ある意味、もう知ってた、分かっていたという諦念に、心は支配されていた。
なんでだろう。
あれから半月近く経つが、一度も涙がこみ上げない。
去年、成田さんが亡くなったときは、その日一日、何も手につかないほどの情動に揺さぶられた。
それなのに。
もっともっと、比べるのもなんだが、この数年の間に逝かれてしまった方々の中では、比べられないほど近しい人だった。
私に最も影響を与えた彼が、逝ってしまったというのに。
この半月間に、二度ほど不思議なことがあり、数回泥酔した。
それ以上のことは、まだ書けない。
だから、もう15年近く前に、彼の久々の新作を含む上映会「プロジェクトINAZUMA」のパンフレットへの寄稿文を載せます。
なんでだろう。
15年前なのに、これ、もう追悼文のようだ。
「それでも平気で生きている」 七里圭
そう言えば、長く伸び過ぎた髪が眼前に落ちてくるのが鬱陶しくて、両手で押さえつけるように掻き上げては、その仕草のまま、よく人と話していたような気がします。「寝耳に水は気持ちいい。それは泳いだ後に水が抜けていく、あの感じ…」と劇中で長島は言いますが、僕にとって『寝耳に水』の感触は、虚実曖昧模糊とした懐かしさを伴うものでした。
井川耕一郎という稀有なる才能に初めて出会ったのは、もう二十年近く前。入学した大学の映画サークルの新入生勧誘上映会で、『ついのすみか』と『せなせなな』を見たときのことでした。上映後の飲み会で、話しかけることもなく遠巻きに、あれがあの映画を作った人かと眺めていたら、突然すくっとその人は立ち上がり、一人飲み屋を飛び出していきました。妙なことに、先輩方はその異変を気にもせず飲み続けている。僕はなおさら好奇心をあおられ後を追いました。深夜の高田馬場の坂をまっしぐらに駆け下りた男は、駅前に停めてあった誰の物とも知れぬ自転車に飛び乗ると、スタンドを立てたまま、猛烈なスピードでペダルを空漕ぎ始めたのです。精魂尽き果てるまでやめようとしない無為の持続。その異様さは、東京に出てきたばかりの僕に、都会の片隅で孤高の求道者を目撃したような高揚した気分を与え、井川耕一郎という存在を深く印象付けました。
つきあいが始まったのはそれから2、3年が過ぎてからのこと。その頃ちょうど井川さんは、鎮西監督の(幻の企画になってしまった)『光線過敏症の女』という脚本を書いていて、僕はときどき呼び出され、感想を求められたり、粗筋を見取り図化する作業(他者の頭を通過させることで、自分で気付かぬ躓きを発見できるらしい。この時、彼がいかに論理的かを思い知った)を手伝ったりしたのです。それが映画に使われた、あの部屋でした。物が少なく生活感の薄い部屋は、一人で住むには広すぎる間取りでしたが、不思議と開放感はなく、逆にどこか張り詰めたような印象がありました。だからなのか、密室劇であるこの映画の狭く切り取られたショットの積み重ねは、妙に当時の記憶を呼び起こします。
その後も僕はあの部屋に通う機会を持ちました。それは自分の手書きの原稿を清書するためにワープロを借りていたからなのですが、井川さんは僕が書いている時、一人にしてくれたのはありがたいが、その間に当時の僕の彼女を連れ出し焼き肉などを食べて、さも楽しそうに帰ってくる。悔しいから冷蔵庫の中の物をいろいろ頂戴したら、なせかカマンベールチーズのことだけ、いまだに恨み言を言われます。
『ついのすみか』を経て『浴槽の花嫁』という封印された作品の後、映画監督井川耕一郎は沈黙し、やはり監督を休止した高橋洋の後を追うように、脚本家としてのキャリアを開始しました。僕が知るこの時期の井川さんは、何かを目指しているのにどこにも行けない苦しみと闘っていたような気がします。Vシネマの枠組みにため息し、ハルシオンや伝言ダイヤルを取材して小説の構想を練ったこともあったはず。カラオケで絶叫して飛び跳ねたり、いつ終わるとも知れぬ長電話をかけてきたりするたび、一心不乱にペダルを空漕ぎするあの時の姿が重なりました。
いきなり断言しますが、井川耕一郎は天才でも狂人でもありません。たぶん、地道な努力の人なのだと思う。狂っているとはどういうことなのか、幽霊のように生きているってどんな感じか、真摯に愚直に追求し続けるその様が稀有であり、実に崇高なのです。
僕が井川さんの影響下にあったのは二十代の半ばまでで、その後は仕事上でつきあう人々も変わり、次第に疎遠になっていきました。やがて美学校という場所が出来てそこで講師を始めたらしいと知り、久し振りに会いに行ったのは、『のんきな姉さん』の脚本を書いていた頃。ホンの直しをお願いしに行ったら、「今、監督作の準備をしているから」と断られました。その時、スタッフの学生らが現れて僕の顔を見るなり、「ああ、なるほど」とか「よく分かりました」などと訳の分からぬことを言う。聞けば、キャスティングで「七里みたいなヤツを探してくれ」と井川さんに指示されたとのこと。へえと興味を覚えましたが、実際にその『寝耳に水』を見たのは、完成して上映も終わって何年も経ったつい最近です。
初めて見たとき、冒頭の水音からすでに背中がゾクゾクしてしまいました。自問不答のモノローグ。昔、親しんだ、あの感じです。回想の中で回想される光景は、いったい誰の思念なのか? 複雑に錯綜する時制と語りについて、批評の言葉に稚拙な僕は気の利いたことを言う術を持ちません。しかし愚鈍にも、映画の良し悪しは、いかに見る者の知性を刺激し、情動を喚起するかに尽きると固く信じているので、そういう意味で、僕にとってこの映画の白眉は、後輩の自殺を幻視した直後に出る、字幕でした。
「それでも平気で私は生きた」。ああ、そうだ。そうなんだ。どんな痛切な思いをしても、平気で生きていくしかないし、平気でなんかいられないから、心は幽離し、分裂し、不明になるのだ。その有様が、時制と語りの混沌なのでしょう。だから、物語の最後で、大島弓子の『ダリアの帯』のごとく意識が老境の懐古に転じたり、抱きしめた妻をストーブの口火と錯誤するのは、ちょっと悲しすぎるとも思います。そんな抑えがきかぬ亡びへの欲望を諫めるように、寝床で夫を受け入れる妻のとろんとした微笑みは、美しい。ああいう美しさをさり気なく捉える視線に、長い長いトンネルをくぐり抜けた作家の成熟を感じました。
|