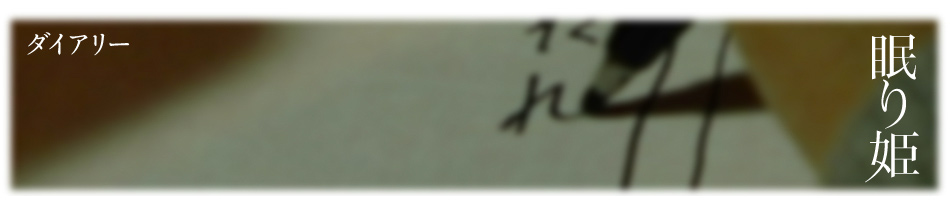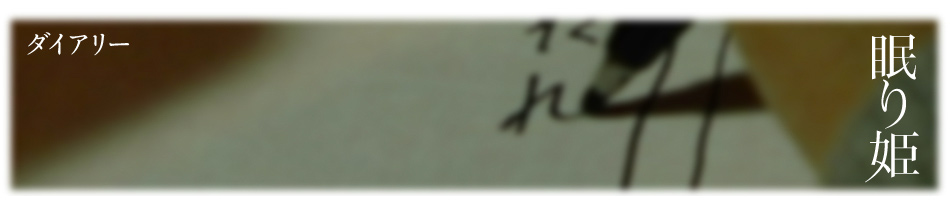|
20代で死ぬだろうと思っていました。
それぐらいノーフューチャーだったし、安酒をかっ食らう量半端なかったし、煙草もショッポをきっちり一日二箱喫ってた。
でも、結局、普通に30代を迎えて、煙草はいつの間にか喫わなくなり、酒は一度にそんなに呑めなくなった。
で、40過ぎてもあんまり生活変わらず落ち着けず、ずるずる生きているうちに、今月とうとう50になります。
半世紀も人間やってきて、いったい何やってたんだという感じ。
気持ちはぐらぐら、ため息つくしかない状況から一向に抜け出せないのだけど、
なんとなく忙しなく、目前のやらねばならない作業に追われることで、日々をやり過ごしている。
なんだかなあと思う。
そんな状態だからなのか、ああこれは見に行こう、行き忘れないようにしないとと、初日に写美へ行きました。
20代のある時期、長島有里枝さんは、僕のアイドルでした。
urbanart#2 展での家族写真の衝撃。
ヌードだからというのと同じくらい、あの家族の表情、カメラを見る穏やかさが異様で。
目に焼きついて、頭から離れなくなった。
それ以前から、写真は人並みに好きで、まあまあ見ていました。
ラリー・クラーク、ナン・ゴールディン、ダイアン・アーバス、牛腸茂雄。
簡単には表れない、触れられない、人の一瞬。
それが永遠に静止してしまうという、写真の摩訶不思議。
ガールズフォトの走りのように言われているけど、長島有里枝は登場から、女の子とか女性とか、そういうフィルターへの違和感を全身で表現していた。
自分との距離、周りの世界との距離、親密と疎外と。
90年代前半、20代半ばまでの僕は、ピンク映画の周辺で助監督をしていたから、エロ業界も近いところにあり、性の資本主義というか、男性に消費される裸という価値観に疲弊していた。
だから、名前をローマ字で冠した写真集の最後の一枚、
深夜の住宅街で自転車にまたがり、キッと振り返る裸の遠景ショットは、『インディアン・ランナー』 で走り去る少年のように、胸がすく思いだった。
でも、とどのつまり、アイドルだったわけで。
一時ものすごく好きになって、遠くから見つめていたけれど、丹念にその後も追いかけたわけでもなく。
『not six』 も本屋で立ち読みだった(はず?だ)し、最近は、ああ小説も書いたのかと知っても読んではいなかった。
まあ、その程度。
で、「ひとつまみの皮肉と、愛を少々」。
タイトルも気に入って、夜の用事の前に恵比寿に立ち寄ったのでした。
写真展で見せられるプロジェクションに、感心したことあまりないのだけれど、この展示のはとても良かった。
変わった趣向があるわけでもない。
ただシンプルに、スライドのように、等間隔で無機質に切り替わり、投影され続ける写真。
デビューから10年、20年を超える(のかな?)作品群が、順番に。
見覚えのある初期の作品、不愉快や情愛や空疎な気持ちが漂いだすようなセルフ・ヌードから、友人たち、愛する男、妊娠、家族関係、息子とのスナップ、最近の生活日常へ。
だんだん齢を重ねていく彼女の顔が、裸が時を刻み、人生の流れ、歳月を感じさせて。
30分くらいだったろうか、立ち尽くした。
月並みな言葉で恥ずかしいのですが、感動しました。
|