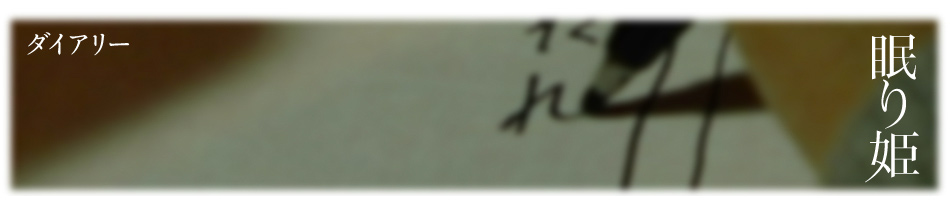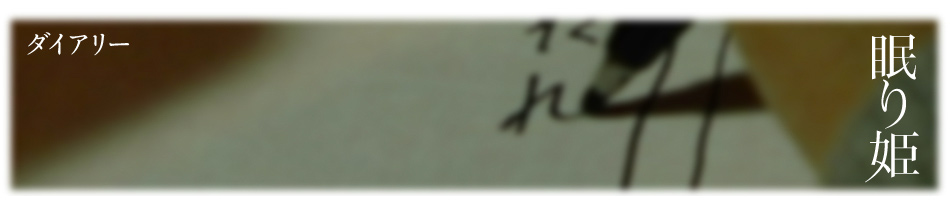|
体調が少し良くなったので、数日振りに一人でふらりと吸い込まれてしまった。
打合せの帰りに、長年のよしみで、慣例だし。
が、一緒に呑むつもりだった彼は、まだ別件ありとのことで、仕方なく。
つどつど立ち寄る、もつ焼き屋へ。
というのは、言い訳に過ぎないが。
隣で呑んでる、常連らしきオヤジ(と言う自分もオヤジだが)の赤ら顔。
なんとなく哀愁漂い、愛らしく、しみじみ。
自分もこのくらいの歳まで、赤ちょうちんに引っ掛かるだけの体力や、余力があるだろか。
感情移入しながらも、しかし、不愛想に本を読みつつ。
ため息つく。
先週は、本当に具合が悪く。
特集上映を前に、つい、堀のことなど思い出したりしてしまったが。
そう書くこと自体、もう一人の亡くなった友人に、雲の上から蹴られるだろう。
酔っ払いの文章は、とんでもない。
先週に、日記を書くつもりだった。
のんきTwitterで伝言もしてもらっていたが、先々週だったかに観た、四半世紀前に脚本を書き、チーフ助監督をしたピンク映画のことを。
書かねばならないと思った。
この週末から上映してもらう劇場デビュー作よりも、もっと遥か前。
確かにいた、もっとうぶで、初期衝動をさらけ出した(と思うのは自分だけだが)無防備な自分を見つけてしまったから。
ところが、「つもり」通りにはいかないのが人生だ。
とにかく文章を書くのが苦手で、時間がかかる。
『ぬる燗』のことを書いたときもそうだったが、あれこれ思い出したりメモしたりするので、結局、一週間はかかりきりになってしまう。
「日」記では収まらない。
と、分かっているので、及び腰。
うだうだと腰重く、目を逸らしていたら、体調を崩してしまい。
おまけに、Web掲載のインタビュー記事の元原稿が送られてきて、びっくり。
うーん、これは、手を入れざるを得ない。
寝たり起きたりしながら、ちまちま言葉をいじるのに、足りない脳みそを持って行かれてしまった。
まあ、それが20年以上ぶりに観た『三十路秘書太股ご接待』について、まだ書きはじめれない言い訳だ。
1995年公開時のタイトルが、『人妻秘書肉体ご接待』だったのは覚えていたが。
(詳細なストーリー紹介とともに、その指摘をすぐにしてくれたブログもあった)
シナリオタイトルは、「平行四辺形」だった。
と、思い出させてくれたのは、つい数日前。
サード助監督として一緒に奮闘してくれた、黒川監督に教えられてだった。
山岡さんのデビュー作となってしまった、あの映画のいきさつについては、書いておくべきかもしれない。
阪神大震災とオウムのサリン事件に挟まれた、ほんのひと月余りに、怒涛のように様々なことが起きた。
往々にして映画製作とはそうなのだが、映画以上に、映画的な日々だった。
そして、あの作品を頑張ったために、結果的に僕は、ピンク映画の監督になることをあきらめざるを得なくなった。
青春の蹉跌だ。
当時は僕は、映画監督になろうとか、なれるとか、本当に全然思っていなかった。
けれど、ピンク映画は撮りたいと思っていたし、いつかピンクを撮るんだろうなと、漠然とだが心構えしながら、助監督をしていた。
が、叶わなくなったのだった。
あのあと、更に延々と、助監督を続ける人生となり。
僕の二十代は終わった。
|