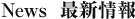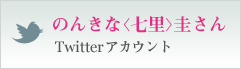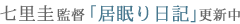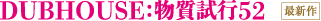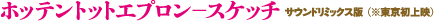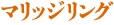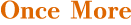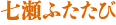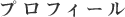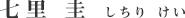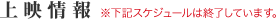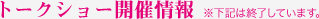- 2013.09.30
- 『DUBHOUSE:物質試行52』25FPS国際映画祭にてグランプリ&審査員特別賞のダブル受賞!!!
- 2013.09.13
- 『DUBHOUSE:物質試行52』9月25日より開催のザグレブ25FPS国際映画祭コンぺ部門へ出品!
- 2013.08.18
- 2013年10/12(土)〜アップリンクXにて『眠り姫』14度目のアンコール上映決定!
- 2013.08.18
- 2013年10/12(土)〜アップリンクルームにて『ホッテントット〜』『To the light』上映決定!
- 2013.05.30
- 2013年6/18(火)京都・同志社大学にて「眠り姫」“アクースモニウム上映” 決定!
- 2013.03.09
- 2013年4/6(土)〜名古屋シネマテークにて特集上映「のんきな〈七里〉圭さん」公開決定!
- 2013.01.01
- 2013年3/2(土)〜大阪シネ・ヌーヴォにて特集上映「のんきな〈七里〉圭さん」公開決定!
- 2013.01.01
- 2013年2/2(土)〜新宿K's cinemaにて『DUBHOUSE:物質試行52』他、アンコール上映!
- 2012.12.26
- 第42回ロッテルダム国際映画祭にて『DUBHOUSE:物質試行52』が公式上映されます!
- 2012.11.10
- 本日より一週間のみの限定公開! 11/16(金)まで、お見逃しなく!
- 2012.11.09
- 上映期間中、劇場ロビーでは、七里作品スチルカメラマンでもある写真家・宮沢豪の作品を展示!
- 2012.11.08
- 特別上映企画「闇の中の眠り姫」アフタートーク、ゲスト:小池昌代さん(詩人・小説家)です!
- 2012.11.08
- 特集上映「のんきな〈七里〉圭さん」予告がYou Tubeにアップされました。
- 2012.11.06
- 吉田広明さん(映画批評家)による特別寄稿がアップされました。
- 2012.11.04
- 昨晩、酔っぱらった監督が階段を転げ落ちましたが、だいじょうぶだった模様です。
- 2012.11.03
- 各日、トークショーゲスト決定! 詳細はこちらをご覧ください!!

2012年/16分/35mm
共同監督/鈴木了二 撮影/七里圭 高橋哲也 カラー/牧野貴 音楽/池田拓実
2010年国立近代美術館における建築家鈴木了二のインスタレーション「物質試行51:DUBHOUSE」の記録映画。建築が生み出す闇を捉えるという当初の意図は、翌年3月11日の出来事により決定的な変化を被る。七里は、展示作品を撮影した光の部分と同じ時間の闇を冒頭に置き、その中に、鈴木が描いた被災地のドローイングを沈ませた。映画館は、闇を内在した建築である。その闇から浮かび上がろうとする映画は、映画館に放たれる光であると同時に、祈りであるかも知れない。七里の現時点での最新作は、メタ映画であり、歴史的出来事への応答でもある。

2004年/87分/35mm
原作/山本直樹 脚本/七里圭 撮影/たむらまさき 音楽/侘美秀俊 編集/宮島竜治
出演/梶原阿貴 塩田貞治 大森南朋 梓 佐藤允 三浦友和
姉との禁じられた愛の記憶を小説に書き、雪山で自殺しようとする弟と、聖なる夜にオフィスで残業する姉。その二人の現在に、記憶=小説がフラッシュ・バックされてゆく。雪山と都会、現在と過去という二つの空間、二つの時間が溶け合う瞬間、弟のささやく声は物語の全てを宙づりにする…。七里は長編映画デビューにあたって、敬愛する山本直樹の同名漫画を原作にし、その漫画の霊感源、唐十郎『安寿子の靴』、森鴎外『山椒大夫』までも射程に収めた。夢のような物語を綴る、淡い光とゆらめく影。貴重な35mmフィルムでの上映。

2007年/80分/DV
原作/山本直樹 撮影/七里圭 高橋哲也 音楽/侘美秀俊
声の出演/つぐみ 西島秀俊 山本浩司
夢は、体が眠っているのに脳は活動している半覚醒状態に現れるが、冒頭、夜が朝へと移りゆくまどろみの時間を映し出す本作は、全編、夢の中の出来事かのように思わせる。ほとんど人の姿が映らず、声や物音など気配だけが画面を満たしている。七里は再び山本直樹を原作に選んだが、この漫画は、幻聴を主題にした内田百間の短編小説『山高帽子』を下敷きにしている。初公開からすでに5年、アンコール上映が繰り返される度に熱狂的なリピーターを増やし続けている異色作。人々がなぜ、この作品に魅かれ続けるのか、それは観た者にしか分からない。

2006年/70分/DV
原案/新柵未成 撮影/七里圭 高橋哲也 音楽/侘美秀俊 池田拓実 人形/清水真理
出演/阿久根裕子 井川耕一郎 ただてっぺい
隠れた場所に醜いアザを持つ少女は、ある日、ネズミ色のフードで顔まで覆った笛吹き男を見かける。笛の音色に引き寄せられるように、彼女は森の中の一軒家に迷い込む。そこには、自分と同じアザを持つ人形がいた。愛知芸術文化センターの「身体」をめぐる連続企画として製作された作品。原案の新柵未成は、『眠り姫』の「手」の出演者でもある。台詞の無いこの映画は、過去7回ライブ上映が開かれ、演奏の度に音楽は進化/深化している。今回はその音源を新たに加えたサウンドリミックス版による上映!

2004年/20分/35mm
撮影/高橋哲也 鈴木明彦 音楽/侘美秀俊 編集/宮島竜治
出演/安妙子 大友三郎
『のんきな姉さん』として撮影開始されたが頓挫し、それまで撮ったフィルムを全く別の短編として再構築したもの。現場環境が悪く同時録音を断念せざるを得なかったのを逆手に取り、効果音と音楽のみで構成。これにより、夢=どこでもない時空間が現れることになった。声が失われた世界での、ボーイ・ミーツ・ガール。欠如を抱えた映像として『眠り姫』、『ホッテントットエプロン』の原型であり、以後の長編を胚胎している重要な作品。「この映画でできたことと、できなかったことが、僕のすべて」とは、七里の言。必見。

2010年/7分+7分/HD
撮影/七里圭 高橋哲也 カラー/牧野貴
音楽/クラムボン 出演/黒田育世
クラムボンのアルバム「2010」に収録された曲『Aspen』のPV。この曲は、ボーカルの原田郁子が祖母の訃報に際して書いたもので、その思いは信頼するダンサー黒田育世に託された。黒田から依頼を受けた七里は、ギリギリの予算で16mmフィルムでの撮影を選択。 長廻し一発撮りで二つのヴァージョンが作られた。今回は未公開の「一本道編」も併せて上映。

2007年/99分/35mm(※HD上映予定)
原作/渡辺淳一 脚本/西田直子 七里圭
撮影/高橋哲也 音楽/侘美秀俊 編集/宮島竜治 村上雅樹
出演/小橋めぐみ 保阪尚希 高橋一生 川瀬陽太 中村麻美 田口浩正
上司との不倫や彼氏とのすれ違いに揺れる微妙な心理を描いた女性映画。オフィスで交わされる視線劇や主人公のつぶらな瞳に宿る色香といった、「普通の」演出もこなしつつ、手や階段、球など、七里作品に特徴的な物体や空間が要所に配されている。助監督経験の長い七里は、準備十日、撮影一週間強、さらに十日ほどで編集という短い日程ながら、職人としての技量を発揮した。

2008年/34分/DV
音楽/鈴木治行
出演/ポン・ジュノ 香川照之
カラックスやゴンドリーが東京で撮ったオムニバス映画『TOKYO!』の、これはポン・ジュノ編のメイキング。インタビュー映像を一切排し、映画の撮影現場における声と音を完璧に録ることで、ポン監督が1カットを撮る迫力ある空気のすべてを捉えた。しかし、そこにはモニター主義への七里の皮肉もやんわり滑り込む。隠れた傑作。

2003年/20分/DV
音楽/侘美秀俊 出演/小池こづえ 演奏/カッセ・レゾナント
Cindyとは、美術家シンディ・シャーマンのこと。彼女が映画女優に扮した、一連のセルフ・ポートレート「Untitled film still」へのオマージュ。スクリーン・プロセスの魔法で「ここ」がそのまま「よそ」になる。めくるめく映像技巧の万華鏡。七里作品の音楽を一手に引き受けてきた、侘美秀俊が率いる室内楽団のために作られた。

1998年/25分+25分/VTR(※デジタル上映)
原作/筒井康隆 脚本/新田隆男 七里圭 編集/宮島竜治 写真/宮沢豪
出演/渡辺由紀 安達哲朗 篠原直美 洪仁順 若松武史
深夜ドラマとして放映された七里の商業デビュー作。原作の設定を逆手に取ったオリジナル劇。事実と真実を巡る刑事の哲学的な尋問と、その刑事がなぜか狙撃の現場にいた理由を追って時間を行き来する副主人公のアクションの、静と動の対比。現実と記憶の区別がつかなくなってゆく世界で、副主人公が父と再会するという感動的な展開。印象的に構成される写真の宮沢豪は、七里の盟友的存在。

1984年/24分/8mm(※デジタル上映)
七里が16歳で撮った正真正銘の処女作。PFF ’85に入選し大島渚に激賞された。突然、人間の体が点滅を始め、それが段々早くなり消滅する奇病が全国に蔓延。対策として踏み台昇降運動が奨励される。自己の存在の意味と没個性社会への問いかけが、踏み台を昇降する機械的な運動のリフレインによって描かれる。
1998年/60分/VTR(※デジタル上映)
脚本/水上清資 七里圭 撮影/高橋哲也 音楽/侘美秀俊
出演/藤崎彩花 桃井マキ 小川真実 今泉浩一 佐野和宏
『羊たちの沈黙』のようなポルノを、と依頼されながら、カフカを意識して作ったというエロスVシネ。尋問する側がいつの間にか尋問される側になるパラドックスに満ちた展開は、「自己の中の他者」を映し出す鏡としての他者、という七里のお馴染みの主題でもある。七里作品の伴走者、高橋哲也をカメラマンとして初起用。
1967年生まれ。高校時代の8mm映画が第8回ぴあフィルムフェスティバルに入選。早大に進学しシネマ研究会に所属。先輩の西山洋一(現・洋市)、高橋洋、井川耕一郎らの手伝いをするうちに、映画の現場で働き始める。鎮西尚一、廣木隆一などの監督作につき、約十年間のあてどない助監督生活を経て、世紀の変わり目に『のんきな姉さん』を監督。諸事情でお蔵になりかけるも、長・短二本の映画として完成し、2004年に劇場デビュー。その後TBS「世界遺産」の構成作家などをしながら、二年の歳月をかけて『眠り姫』を自主製作。また愛知芸術文化センターの委嘱で『ホッテントットエプロン-スケッチ』、2007年には『マリッジリング』を監督するが、以降、長編作品を発表していない。監督歴14年。「年数にも満たない作品数しか残せていない。もうダメかもしれない…」と弱音を吐くが、『眠り姫』は公開から6年経った今もアンコール上映を繰り返し、『ホッテントット』のライブ上映もたまに再演される。穏やかな風貌の下に、意外に硬派な顔も潜ませている。

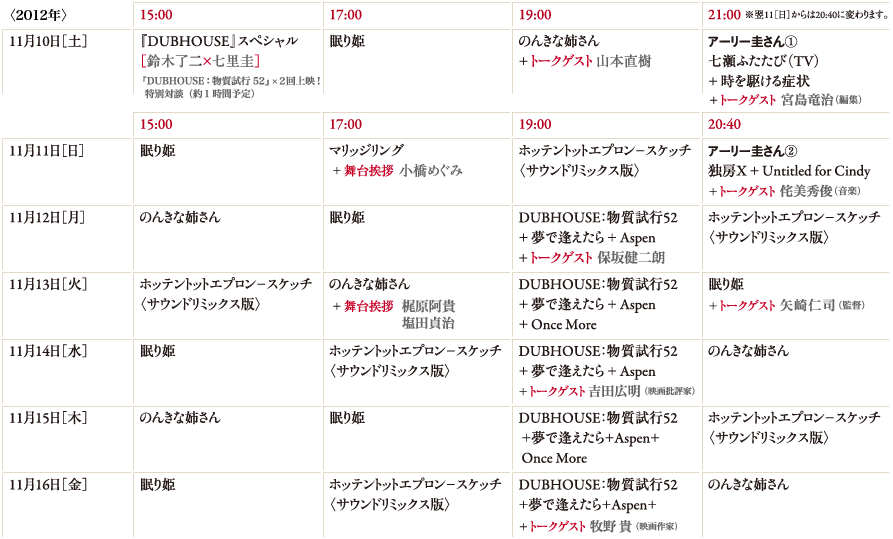
※短編集の上映回は、『Once More』上映付きの回と、トークショー付きの回とがありますのでご注意ください。
※短編集の上映順は、『夢で逢えたら』→(『Once More』)→『Aspen』→『DUBHOUSE:物質試行52』の順番になります。

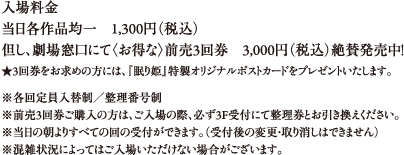
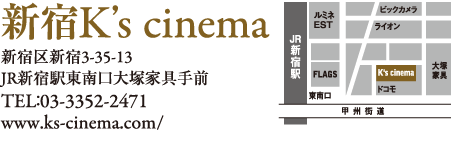

- 2012年11月10日(土)
- 15:00 鈴木了二×七里圭(『DUBHOUSEスペシャル』)
- 19:00 山本直樹(原作者)× 七里圭(『のんきな姉さん』)
- 21:00 宮島竜治(編集)× 七里圭(「アーリー圭さん(1)」)
- 2012年11月11日(日)
- 17:00 小橋めぐみ(主演)※舞台挨拶(『マリッジリング』)
- 20:40 侘美秀俊(音楽)× 七里圭(「アーリー圭さん(2)」)
- 2012年11月12日(月)
- 19:00 保坂健二朗(東京国立近代美術館)× 七里圭(『DUBHOUSE:物質試行52』他短編集)
- 2012年11月13日(火)
- 17:00 梶原阿貴、塩田貞治 ※舞台挨拶(『のんきな姉さん』)
- 21:00 矢崎仁司(映画監督)× 七里圭(『眠り姫』)
- 2012年11月14日(水)
- 19:00 吉田広明(映画批評家)× 七里圭(『DUBHOUSE:物質試行52』他短編集)
- 2012年11日16日(金)
- 19:00 牧野貴(映像作家)× 七里圭(『DUBHOUSE:物質試行52』他短編集)
七里圭という映画作家にとって、35ミリフィルムで長編デビューできたことは、幸福であったのか不幸であったのか。フィルムの質感、その闇への、光への感度に魅せられてしまった者として、七里はフィルム=映画にひたすら忠実であろうとし続ける。デジタルの時代にあって、それはアナクロニックな営みであるだろう。しかし彼は、自身の歴史的位置に対して責任を取り続けているのであり、その意味で彼は極めて倫理的な作家なのである。ここに、「映画」にこだわり続ける七里のこれまでが明らかにされる。七里の映画とは、今ここをどこでもない、映画そのものとしかいいようのない時空間に変容させる、知的にして官能的な企みである。見る者は、夢のような時空に心身を遊ばせると同時に、「映画とは何か」に必ずや思いを致すだろう。この上映は回顧であるに留まらず、七里圭という映画作家の―いや、「映画」の―これからを見据える営みとなるはずである。
七里ふたたび ~ 七里圭作品を改めて解説する
本稿では、筆者がK's cinemaでの七里圭特集上映に際してチラシのために書いた作品解説の原型を掲載する。チラシ原稿は字数制限を一応考慮したものの、字数を大きく超えたものもあり、実際のチラシ文は筆者が書いたものを宣伝担当が圧縮したものとなっている。本来依頼原稿は最終形がすべてであり、作業過程の草稿の類は表に出すべきものではないのだが、筆者の元々の原稿が、各作品解説が相互に連関し、七里作品の全体を照らし出すものとなっていたということ(ただ、これは或る作品で書ききれなかったことを他の作品の解説に含ませたりしているのでそう見えるだけなので、買いかぶりではないかと思うのだが)、また、切り取った文章の中に七里作品を理解するための興味深い文言が含まれている、ということで、できればこれを残したいという宣伝担当の意向もあり、ホームページに掲載することになった。と言って、ただ元の原稿を載せるだけでは筆者の自己満足に終わりかねないので、作品解説で書き切れなかったことや筆者の個人的見解、回想を含め、七里圭と言う映画監督について、こちらも「のんびりつらつら」書いてみようと思う。
『七瀬ふたたび』(第9,10話、1998年、VTR)
七里圭の商業デビュー作。1998年4~7月、TV東京の深夜ドラマ全十三話(全てに七里は助監督としてつく)中、エピソード「心的力域」の後半部(ちなみに前半部は山崎貴演出)を担当。超能力者が抹殺される時代、狙撃されるヒロインを時間遡行者が救うという前半のエピソードを、後半の七里は、一連の事件を捜査、彼女を尋問する刑事を導入してオリジナルに再構築。刑事役は当初原作者の筒井康隆が演じる予定だった。事実と真実を巡る刑事の哲学的な尋問と、なぜか狙撃の現場にいたその刑事を追って時間を行き来する副主人公のアクションの静と動の対比。現実なのか記憶なのかもはや区別がつかなくなってゆく世界で、副主人公が父と再会するという感動的な展開になってゆく意外性。劇中の印象的なモノクロ写真を担当した宮沢豪は七里の盟友的存在。
筆者がチラシ文を書いた時点では、処女作『時を駆ける症状』(1985)の上映は決まっておらず、従って『時を駆ける症状』に関する文は筆者が書いたものではない。『時を駆ける症状』は無論筒井康隆のジュブナイルSFの古典『時をかける少女』のもじりであり、しかしパロディかと思いきや、実際見れば、真っ当な青春SFであるという驚きが鮮やか。「時を駆ける症状」という言葉を字義通りに解釈し、時間を飛ばす=コマ撮りとして演出。ラストの怒涛のコマ撮りは映画を作ることの始原的喜びに満ちている(後半はほとんど一人で作業していたというから、実際の現場は相当大変だったとは思うが)。映画を撮り始めたのも、商業デビューも筒井康隆がらみであったわけで、その事実は、七里の映画的想像力の出自を考える上で示唆的である。少年時代はSFを好んでいた旨監督から聞いた気がするが、その後の実験的な作風は、SF好きに由来するかもしれない。
『独房X』(1998年、VTR)
『羊たちの沈黙』のようなポルノを、と依頼されながら、カフカを意識して作ったというVシネ。刑務所のさらにその中の檻という二重の檻に封じ込められた女囚が実は刑務所の中心であることが判明したり、尋問する側がいつの間にか尋問される側になっていたりとパラドックスに満ちた展開。自己の中の他者を映し出す鏡としての他者、という七里監督作品におなじみの主題が既に表れている(以後の作品では端的に離人症や分身として現れる)。高橋哲也を初めてカメラマンとして起用した作品。
『七瀬ふたたび』も『独房X』も、物語の枠組みとして、尋問という形式を取っている。二人の人間が対峙し、言葉を交わすことで、心の中が露わになってゆく。しかも、尋問される側ばかりでなく、というかむしろ、尋問する側の。尋問は、実は一方的な関係ではない。尋問する側もまた、心を暴かれるのであり、尋問する側、される側、それぞれが相手を照らし合っている。こうした鏡のような対関係が、その後は『眠り姫』における離人症や『ホッテントットエプロン―スケッチ』における人形として、要するに分身として現れてくる。七里は、こうした人間心理に関して、木村敏やその弟子の長井真理、古井由吉『杳子』の影響を語っているのだが、筆者としては、分身主題よりは、権力関係、あるいはもっと広く、人間関係の(逆説的)ダイナミズムが興味深い。
七里は早稲田大学在学中シネ研に所属、OBに西山洋一(現、市)、高橋洋、井川耕一郎らがいたが、それぞれに批評的才能の持ち主でもあり、七里の映画に批評性を感じるのは、こうした先輩方の影響もあるのかもしれないと思う。七里は西山監督の『ぬるぬる燗燗』(1996)の助監督を務めたり、高橋、井川編集になる大和屋竺のシナリオ集『荒野のダッチワイフ』の一部作品解説を書いたりしている。高橋の伝手で、タウン誌の調べ物のバイトをしたり、同じくシネ研の先輩飯塚裕之の紹介でTBS『世界遺産』の構成作家をしたりもしているが、作品世界を作り出すにあたって、ただ感性に頼らず、何らかの原案を元にして調査と思考を繰り返し、練り上げてゆく手法は、こうした調べ物仕事から来てもいる、と本人は言っている。卒業後はピンク映画などの現場で助監督修業を積むが、中でも西山洋一、鎮西尚一の現場を多く務めた。
『Untitled for Cindy』(2003年、DV)
それまでいくつかの現場で出会っていた侘美秀俊に『独房X』の音楽を依頼した七里に対し、今度は侘美から自身が率いる楽団カッセ・レゾナントのイベントで流す映像を、と依頼がある。写真家シンディ・シャーマンが映画女優に扮した一連のポートレート・シリーズUntitled film stillsへのオマージュ。スクリーン・プロセスを用い、「ここ」がそのまま「よそ」になる。何重もの焼き付け、速度の変化、色味の変化など短い中に様々な映像技巧が凝らされている。
『夢で逢えたら』(2004年、35mm)
『のんきな姉さん』として撮影開始されたが頓挫(長編は仕切り直して作られた)、それまで撮ったフィルムを短編としてまとめたもの。現場の録音環境が悪くて同時録音を断念せざるを得なかったのを逆手に取り、台詞なし、構成された音と音楽のみで構成。これにより夢=どこでもない時空間が現れることになった。文字通り原『のんきな姉さん』であり、欠如を抱えた映像として『眠り姫』、『ホッテントットエプロン』の原型であり、以後の長編を胚胎しているという意味で重要な位置を占める短編。
2000年代に入って、七里の作品はいよいよ実験的なものになってゆく。これまでの仕事の過程で出会ってきた宮澤豪、高橋哲也、侘美秀俊ら、共謀者=スタッフが固まってきて、自分の意向通りの映像=音響を作れるようになってきたことも大きい(その後、新柵未成、池田拓実、牧野貴らも加わる)。七里において実験的とは、様々な出典を重層的に組み合わせること(これについては、上記のような調べ物仕事の影響に加え、『のんきな姉さん』原作者である山本直樹の作風の影響もあるだろう)、映像=音響に何らかの欠如を抱えること、として現れる(それは映画の内容においても言えることかもしれない。『のんきな姉さん』の姉弟にすでに両親はいないし、原作・脚本作品『犬と歩けば チロリとタムラ』において、主人公は飼い主に捨てられる犬である)。何かを欠如させるということは、まず、現実を異化し、どこでもない時空を立ち上げるという意味と、その欠如した何かを、観る者が想像的に補うよう促すという意味がある。七里は、映画というものがそう簡単に立ち上がってくれるものと思っていない。映画がどうすれば成立するのか、そうした疑問を常に映画作りの初めにおいており、従って、彼の作る映画はどこかメタ映画的な要素を常に持つことになる。しかし、そうした姿勢が、商業映画と多少の齟齬をきたしてしまう事もまたありうる事態であって、七里の初の商業長編映画が一旦頓挫してしまうのも、あるいは偶然ではなかったのかもしれない。
『のんきな姉さん』(2004年、35mm)
長編映画デビューにあたって、七里は敬愛する山本直樹の同名漫画を原作に選択する。その漫画自体、唐十郎の小説『安寿子の靴』、さらにその霊感源、森鴎外の『山椒大夫』を元にしている重層的な構造。姉との近親相姦の記憶を小説に書き、雪山で自殺しようとする弟と、都会のオフィスで残業する姉(神出鬼没な課長三浦友和に注意)。その二人の現在に、記憶=小説のフラッシュ・バックが挿入されてゆく。雪山と都会、現在と過去という二つの空間、二つの時間が遂に溶け合うに至る瞬間、弟のヴォイス・オーヴァーがこれまで語られてきた全てを宙づりにする(声は、次作『眠り姫』で一層重要な役割を演じる)。七里の35ミリ・フィルムで撮られた長編はこの一本のみであり、七里は35ミリで長編デビューできた最後の世代ということになる。
『眠り姫』(2007年、DV)
夢は、体が眠っているのに脳は活動している半覚醒状態に現れるが、夜が朝に変わる時間を長廻しで捉えた冒頭を持つ本作は、全編が夢の中の出来事であるかのような作品(というか七里の作品はすべてがそのようなものとして作られている)。『のんきな姉さん』公開時に劇場ロビーのモニターで流す映像として製作が始められ、その後長編として作り直された。『眠り姫』という架空の映画のサウンド・トラックに後から映像が付けられた(まるでデュラスの『ヴェネチア時代の彼女の名前』のように)という設定どおり、声、物音などが重要な役割を演じる。殆ど全編人物が映らず、気配だけが画面を満たすという特殊な作り。サウンド・トラックのみで、真っ暗闇の中で上映?されるという試みも行われた。山本直樹の原作は、これも内田百閒の『山高帽子』、『サラサーテの盤』を下敷きにした重層的な構造を持つ。いくつかのショットで用いられる8ミリ・フィルムの質感にも注目。
『ホッテントットエプロン-スケッチ〈サウンドリミックス版〉』(2006年、DV)
愛知芸術文化センターによる、「身体」をテーマとした連続映像企画として委嘱された作品(これまでにダニエル・シュミット『KAZUO OHNO』など)。原案は七里が教えていたワークショップの学生だった新柵未成(『眠り姫』に「手」の出演もしている)。身体の痣に屈託を持つ少女が、ハーメルンの笛吹き男に出会い、その男の住む?ダンボールハウスから、森の中の一軒家に入り込む。そこには自分と同じ痣を持つ人形がいた。窓のないダンボールハウスとダンボールで覆われた一軒家は、女性の身体の比喩であるが、同時に闇をはらむ空間として映画館でもあるかも知れず、とすればこれもまたメタ映画とみなすことができ、『物質試行』につながってゆくだろう。一旦完成したものの、音楽が満足いかず、改めて生演奏上映会を開催、さらにサウンドをリミックスして現行版が作られた。
『マリッジリング』(2007年、35mm、上映はHD)
瀬々敬久『泪壺』と共に、渡辺淳一小説の映画化企画として依頼された作品。準備十日、撮影一週間強、さらに十日ほどで編集と短いスケジュールながら、助監督経験の長い七里は職人としての技量を発揮(実は『のんきな姉さん』の撮影期間も十一日だったという)。映画はオフィス内での不倫関係を描くが、オフィス内の視線のやりとりで人物の心理の微妙な変化を感じさせるなど、「普通の」演出も示しつつ、マリッジリングをはめた「手」や、階段、球、観覧車など、七里作品に特徴的な物体や空間を要所要所に配して自分の映画にしている。どこか暴力的なヒロインの同僚矢沢心や、神出鬼没な元課長(『のんきな姉さん』の三浦友和も「課長」だった)田口浩正(七里は田口の監督作『マインドゲーム』で演出補についている)など脇役も魅力的。
いささか個人的な話になるが、筆者が七里圭監督と知り合ったのは、監督が『のんきな姉さん』を撮った後のことだ。映画批評家の遠山純生氏の主宰した、映画関係の各方面ライターを集めた飲み会の席でのことだった(七里は、遠山氏が編集していたシリーズ、「E/Mブックス」の最新刊『アレックス・コックス』に寄稿していた)が、映画監督だと自己紹介され、飄々とした風貌なので油断していたが、聞けば長編映画を撮っており、しかも何と撮影が田村正毅(たむらまさき)だという。田村正毅といえば小川紳介のカメラマンとして神話的な名前であり、こののんびりした人があの田村正毅と、と、思わず絶句したが、気を落ちつけたところで、PFFで最年少入賞の経験あり、と追い打ちを食らい、さらに一驚を喫した。その後『眠り姫』、『ホッテントットエプロン―スケッチ』、『マリッジリング』と出来あがる度に見せてもらってきて、また過去にさかのぼって全ての作品を見た。お互い住むところが近いこともあり、飲む機会も何となく増えて、その過程で、彼の映画の好み、詳しい経歴なども知るようになったわけである。
七里監督との付き合いが、いま現にこうした形で作品理解を深めるという意味で役に立ってはいるのだが、そもそも筆者には、映画の作り手と個人的に知り合いであるということが良いことなのかどうか迷いがある。作品に興味がある以上、それを作った作り手に関心が向くということは自然であり、彼(ら)の話を聞き、それを伝えることも批評家の仕事のうちとは思うのだが、その作り手を個人的に知っていることが、悪口を言いにくい、という卑近な不都合を生み出すばかりでなく、冷徹な判断を曇らせるかもしれない。批評家にとっては作品がすべてであり、作り手が何を意図しようと知ったことではない、出来あがった結果だけで判断すべきだ、という考え方にも一理あると思っている。筆者はどちらかというと、あくまで作り手とは一歩距離を置き、あくまで作品を通して作り手と関わることを望むものだが、しかし一方で、人間いずれコミットすることなく何かと関わることはできないのであり、完全に客観的で冷徹な判断はありえない、とも思う。ともあれ、付き合ってゆくにつれ、七里圭という人物そのものへの信頼は増すことはあっても減ることはなく(むろん聖人君子である筈もなし、ものを作る人間であるからには必ずどこか一筋縄でいかない所があることを踏まえたうえで)、彼が作るものであるならば、例え失敗作であれ、その失敗は、映画というものやその現状について、何かを教えてくれるものだ、という確信を筆者は持つことができる。これは現今の映画製作状況下にあって得難いことだと思う。
『Once More』(2008年、DV)
ポン・ジュノをはじめ、レオス・カラックス、ミシェル・ゴンドリーによる東京を主題とした2008年のオムニバス『TOKYO!』のポン・ジュノ篇「シェイキング東京」のメイキング。他のメイキングと違い、インタビュー映像を一切排し、もっぱら撮影現場のみを捉える。そこには映画について常に考えながら撮る作家、としての七里のポン・ジュノへの批評的視点がある(その意味は見れば分かる)。
『Aspen』(一本道編、白樺編)(2010年、HD)
クラムボンは2010年発表のアルバム『2010』の全曲にPVを作ることにするが、その中の一曲『Aspen』をダンサー黒田育世に依頼、黒田はかねて知っていた七里に声をかける。自然の中で踊る黒田は、自然と溶け合うようでもあり、自然の中でこそ人間という異物性を露わにしているようでもある。二つのヴァージョンが作られたが、「一本道編」の方が採用された。撮影は16ミリで行われ、デジタル化された。
『DUBHOUSE:物質試行52』(2012年、35mm)
七里は、建築家鈴木了二から2010年の東京国立近代美術館におけるインスタレーション作品「DUBHOUSE:物質試行51」の撮影を依頼される。光の動きによって建築が生み出す闇を捉えるという当初の意図は、2011年3月11日の出来事によって決定的な変化を被る。七里は、インスタレーション撮影部分に相当する時間数の闇を冒頭に置くことにし、その中に可視ぎりぎりの明度で、鈴木が被災地に赴いて描いたドローイングを沈ませた。「闇を作る力がある」建築とは、闇を内在した建築としての映画館であると共に、自然に抗して建てられ、自然によって破壊されるという意味で災害=闇を生み出すものでもある。一方その闇から浮かび上がろうとする映画は、映画館の中で放たれる光であると同時に、祈りでもあるかも知れない。七里の現時点での最新作は、メタ映画であり、同時に歴史的出来事への応答でもある。
七里の現時点での最新作二本(『Aspen』と『DUBHOUSE』)は、共にフィルムで撮られている。折からコダック社は、デジタル映像の普及に伴い、フィルムの製造を中止した(2012年3月1日)。富士フィルムも来年2013年にはフィルム製造中止の予定という。そうした状況下でのフィルム撮影は、まさに反時代的な行為と言える。しかも、これらの作品においては(特に『DUBHOUSE』)、黒味、可視ぎりぎりの光など、現像技術も含めて(カラリングは現像所に勤める実験映画作家、牧野貴が行っている)フィルムの限界に迫るような試みがなされており、まさに七里によるフィルムへの挽歌のようである。七里がこれからもフィルムを使い続けるのかどうかは不明だが、「映画」が「フィルム」と同義であることが最早自明ではなくなった現在以後、七里がどのような「映画」を撮ることになるのか。七里の進む道が、すなわち映画の未来なのだ、と言えば、さすがに言いすぎではあろうけれど、その気概で七里監督には「映画」を作り続けていただきたいと思う。
「美しい普遍『ヴァンダの部屋』」+「暗い部屋に、魂が。」
※2004年3月21日当時、今はなきWeb@Esquireに寄稿された、七里圭監督による『ヴァンダの部屋』評、及び、それに併せて記載された吉田広明さんの批評(美しい普遍『ヴァンダの部屋』)を上記より特別にお読みいただけます。